安冨歩著、「生きる技法」を読みました
安冨歩著、「生きる技法」を読みました。
こんな本があったのか~!
帯の言葉
「助けてください」と言えた時、人は自立している。
この言葉の意味を知りたくて、本を見た瞬間、アマゾンに移動し買っていました。
「自立」の反対は「従属」という言葉で表すことができる。
不本意に従属することなく、自分らしく生きていく。
それが自立であり、人は一人では生きていくことはできない。
だから、自分らしく生きることをサポートし助けてくれる仲間や友達の存在が大切である。
そういうことらしい。
「生きる技法」が出版されたのは2011年12月。私がこの本に出合ったのはつい最近、2019年11月のこと。私が購入した本を確認すると第14刷発行、と書かれています。
それだけ多くの人に影響を与え、読まれている本、ということになります。
1.著者、安富歩氏と本について
著者は京大卒。東大教授。
そうそうたる肩書とは裏腹に、前妻のモラハラに悩み、母親との関係に悩み、「死にたい」と思いながら生きてきたというのです。
本を読んで、とても素晴らしい内容だったので、「他の本も読んでみたい」と思って調べてみたら、まさに「自分らしく」生きている方の代表みたいな方でした。
きっと苦しみぬいた末にたどり着かれたのでしょう。
数年前からは女性の服装で教壇に立たれているらしい。
昨年の衆議院選挙では、令和新撰組から出馬していたらしい。
お誕生日は3月22日。
22日生まれの人には影響力のある人が多い。(イチローさんも22日、10月22日生まれ)
まったく存じ上げなかった・・・
先ほど書いたように、この本の存在を知ったのはつい最近。
今だからそれなりに理解できると思う反面、もっと早く出会いたかった、とも思います。
すでに2回読んでみたけれど、何度も読み返したい素晴らしい本です。
この本は自分を大切にすることに関して、論理的に、そして包括的に書かれています。
論理的といのは「命題」を証明する形で進めていることからも明白。
包括的というのは、私は「自分を愛する」ということに関して、大きくわけて、二つのステージがあると思っていて。
- マイナス側から0へ(被害者からの脱出)
- 0からプラス側(自主性をもって生きる)
この2つのステージ両方とも扱っている点において包括的。
自分を愛する、というと、どちらかという一つ目の「マイナス側から0へ」のステージの説明と繋げられることが多いと思うのです。
ですが実際は、プラス側に向かえば向かうほど、「自分を大切にする」ということは分かりづらくなる。
それは、別の言葉でいうと、自分軸で生きる、とか、魂の望むことにそって生きる、というような意味に近くなってくるからで。
そのためには「魂の望み」や「ハートの声」、はたまたスピリチュアル的に言うと「ハイヤーセルフ」なるものを、自分が感じ取れる必要があります。今はやりの「直感」とも通じる部分だと思いますが。
ところが、今まで他人の評価や、外側を気にして生きてきた私たちにとって、いきなり「自分の内側」を感じるということ自体、全く知らない外国語を理解しようとするようなもの。
その難しさは、著者も「盲点」という言葉を使っています。
私たちの周りの大人たち(親や先生など)は、大人たちにとって正しく、都合の良い「良い子」に育てるべく、飴とむちを駆使します。それによって、子供たちは、子供たち自身にとっての「正しい」「気持ちいい」「しっくりくる」という「感覚」を感じないようになってしまうのです。
そして、私たちは自分にとっても「正しい」「しっくりくる」感覚が、周りの大人の「正しさ」と相いれないと、自分を「悪い子」と思うようになる。それが「自己嫌悪」につながります。
この「自己嫌悪」が、自分にとっての「正しさ」や「成長」につながることを阻む「盲点」になるのだそうです。
ここからは少し、「生きる技術」に出てくる言葉について解説します。
2.「自愛」「自己愛」「自己嫌悪」
私自身、
自分を愛するとか、自分を大切にする
ということに2009年ごろから注目していました。
本やDVDなど、当時は日本語ではあまり見つけられず、英語のオーディオブックなどからも「自分を愛する」ことについての情報を探し出してきては、自分なりにトライ&エラーを繰り返しながら、それをブログに綴ってきました。
「自愛」と「自己愛」は似て非なるもの。
「自愛」は自分を大切にし、自分のありのままを受け入れること。
一方で、「自己愛」は「自己陶酔」。
この「自己愛」はあるがままの自分ではなく、他人に押し付けられた理想像を、自分にないものとして「嫌悪」し、その押し付けられた理想像に足りない部分を偽装し、その偽りの自分に酔っている状態。
つまり、自己愛の根底にあるものが、ありのままの自分を受け入れられないという「自己嫌悪」。

思わず思い出したのは渡辺直美さん。自愛の塊ですね~。だからイキイキ輝いていて、周りからも評価されるんですね~。
私たちは、他人に押し付けられた理想像から自分に足りないものを身に付けて生きていくのではなく、自分の内側に本来持っている「個性」を伸ばし、活かして、自分らしく生きていくことが重要だということが分かります。
3.「自愛」と「人間関係」の秘訣
こうして見てみると、当然ですが、人間関係においても「自愛」に基づく関係性が望ましいのは予想がつきます。
著者によると、人間関係には、「創造的構え」と「破壊的構え」そして、その両方を持ち合わせた「葛藤の構え」があるそうです。
「創造的構え」は自分の都合の良い理想像を相手に押し付けることなく、その人のありのままの姿を探求する姿勢。
一方、「破壊的構え」はその逆で、相手を思い通りにコントロールしようとし、自分の期待に添わない行動には、批判したり、無視したりして、相手に「罪悪感」を抱かせようとする姿勢。
モラハラ、パワハラなどは、破壊的構への究極的現れ、ということでしょうか。
結婚も、相手に自分のないものを求め結婚したはいいけれど、相手が期待通りに行動してくれないと、腹を立てる。無視する。う~ん、どこかで聞いたことがあるような・・・(苦笑)
相手の光を見る、本当の姿を見る、可能性を信じる、などなど。表現は様々ですが、相手の「ありのままの姿を【探求する】姿勢」を皆が持つことができたら…誰とでも素晴らしい人間関係が築けることでしょう。
言うは易く行うは難し、ですが・・・
4. 自由、夢、人生の目的と「感覚」を感じる重要性
自由と聞くと、何を思い浮かべますか?
私は選択肢が増えることだと思っていたのですが…
選択肢は無数に存在し、どれが「正しい選択か」などということは、それこそ、死んでからじゃないと分からない、そういったもののようです。
なので、自由とは選択肢が増えることではなく、「思い通りに成長すること」だそうで。
著者は「思い通り成長する」ことを、植物の成長に例えていました。自然に、ありのままに、自分が心から望む方向に、といった意味あいだと理解しました。

「思い通りに成長する」ためには、自分の心の声を聞くこと、つまり自分の感覚を感じられるようにならないといけない、ということですね。
特に今の世の中、情報が溢れかえり、自分が心から望むことを感じ取ることは、さらに難しくなっているのではないでしょうか?
そして、もしその「声」を聞くことができたら、勇気をもって自分を貫くのみ、だそうです。
大体、人生の目的というのは、言語化できるようなものではなく、言語化している時点で何かの押し付け、なんだとか。
ただし、言語化は難しくても、自分が人生の目的に向かっている、ということは感じることができる。
ここまでくると、私にはちょっと理解できない領域で、ただ文字を追って「へぇ~、そんなもんなのね~」という状態です。
「夢」というのはあくまでも、その「人生の目的」におけるマイルストーンだそうです。
そんな、自分でも中々感じることが難しい状況の中で、頼りになるのは本当の「友達」の存在です。
本当の友達とは、「創造的構えをベースにした関係性」ということだと思います。
そして、この本の帯にも書かれている
「助けてください」と言えた時、人は自立している。
とは、
- 自分の物的利益のために人からの評判も顧みず相手を利用したり(利己主義)、
- 見せかけ上の人からの評判のために、物的利益を顧みずに自分が自分自身を正当に扱わなかったり(利他主義)
する人達から離れ、自分自身も相手も尊重し、助け合い、可能性を信じあえるような関係性を、人との間に築き上げていくことで、自分をのびのびと成長させていくこと。
さらに、感覚を取り戻し、のびのびと成長する過程では、「勇気」が必要な場面に出くわす。
そんな時、安心して助けを求められる人間関係があれば、不本意に他人との従属的な関係に執着しなくても、周りの協力を得て、自立して生きていける、というのが現時点で私がこの本から得た答えです。
とにもかくにも、自分が感じるべき感覚、つまり
- 心の声を聞くとか、
- ハイヤーセルフとコミュニケーションをとるとか(ハイヤーセルフというのは、私の解釈で、著者はそのような言葉はまったく使っていません。)
それが感じられるかどうかがカギである。
と同時に、感じようとして感じられるものではない、とも言っています。
なら、どうしたらいいのよ!
って思いますが、まずは「感じられるようになりたい」と願うことだそうで。
やはり、「感じられるようになる」ことに執着すると、「できない…」とまた自己嫌悪へのループにはまることになります。
なので、執着せずに、「願うことが大切」ということになるようです。

5.まとめ
まだまだ理解しきれていない部分があります。
なので、再読し理解が深まったら、またこの文章も修正していきたいと思います。
そして、理解にとどまらず、自分の人生に落とし込んでいけたらと思います。
とりあえず、今は、自分の感覚を取り戻すことを願いながら、ひとまずこの文章を終わりにします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
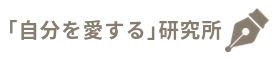

智子さん、あらためて文章を読ませていただき、胸があつくなりました。
立春、いいスタートが、切れそうです。
ありがとうございました
美香さん、こちらこそ読んでいただきありがとうございます。益々素晴らしい一年になりますように。(智子)